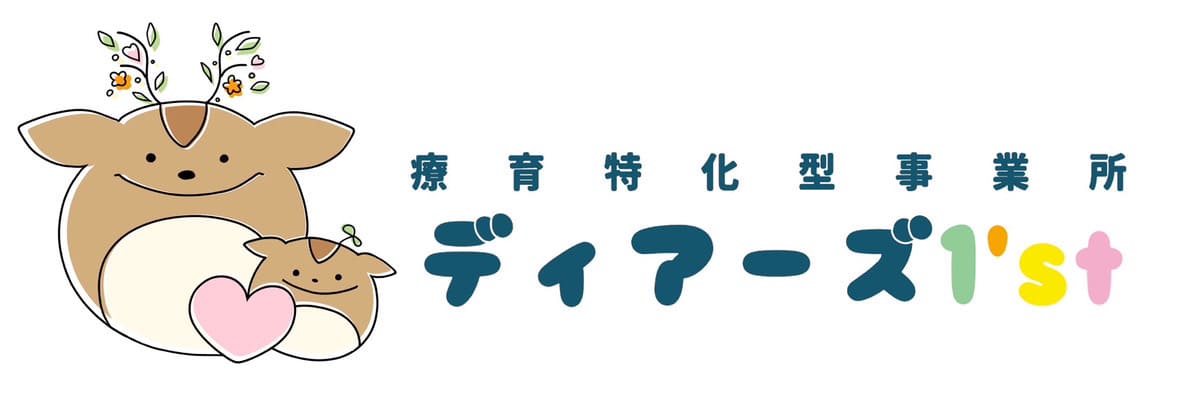同じ動きをくり返す“クセ”のように見える行動が、生活や健康にどのくらい影響しているのか。常同運動症(Stereotypic Movement Disorder)は、その線引きを明確にし、支援の方向性を定めるための診断名です。
目次
1. 定義と診断の基本(DSM-5-TR / ICD-11)
2. どんな“動き”が該当する?――具体例と特徴
3. 似て非なるもの:チック・強迫行為・不随意運動との違い
4. どれくらい起こる?――有病率と関連条件
5. なぜ起こるのか:神経生物学と遺伝研究のアップデート
6. 生活への影響とリスク:自傷への備え
7. 介入の実際:薬よりまず行動療法、そして環境づくり
8. 受診の目安と相談先
9. 最新トピックで変わる見立て:疾患横断の視点
10. 今日から使えるミニ・チェックリスト
まとめ
参考・出典(主要)
1. 定義と診断の基本(DSM-5-TR / ICD-11)
常同運動症は、目的のない反復的・定型的(パターン化した)運動が早期発達期(多くは3歳未満)に始まり、日常生活に支障を及ぼす、あるいは自傷を招く場合に診断されます。物質・薬剤や他の神経発達症などでは説明できないことが条件です。DSM-5-TRの要点(A~D基準)と、「自傷を伴う/伴わない」などの特定用語が整理されています。ICD-11でも同様に、6A06として「自傷あり/なし」の区分が示され、チック障害や抜毛症などは除外と明記されています。日本語訳は学会ガイドライン上、「常同運動症/常同運動障害」の併記が用いられます。
2. どんな“動き”が該当する?――具体例と特徴
代表例は手のひらひら(手指のフラッピング)、体ゆすり、頭打ちつけ(ヘッドバンギング)、自分を噛む/叩く、顔・口周りの反復運動など。多くは興奮・集中・退屈・不安の場面で増え、注意転換で一時的に止まりやすいのが特徴です。自傷を伴う型では眼突き・顔たたき・唇や手指の噛みなどが問題になり、安全対策が必要になります。
3. 似て非なるもの:チック・強迫行為・不随意運動との違い
- チック:突発的・素早い・非律動的な運動/発声で、抑えると苦痛(プレモニトリー感覚)を伴い、一時抑制→解放感という経過をとりやすい。常同運動はより律動的で持続的です。
- 強迫行為(OCD):不安や侵入思考を打ち消すために目的的に行う反復行動。常同運動は快い/“しっくりくる”感覚が語られることがあり、目的性が薄い点が異なります。
- 他の不随意運動(アテトーゼ・舞踏運動・ジストニア・振戦など):発現様式・誘因・随伴症状が異なるため神経学的鑑別が重要です。臨床ではMSDマニュアルの表が有用です。
4. どれくらい起こる?――有病率と関連条件
原発性(発達に大きな偏りのない)の運動常同は、単純型は幼児期の子どもで広く見られ、複雑型は3〜4%程度との報告があります。自閉スペクトラム症(ASD)では運動常同の合併率が高く、メタ解析では中央値約52%(研究により21.9〜97.5%)とされます。報告間の幅は大きいものの、ASDや知的能力の程度が強いほど頻度が高い傾向が示されています。臨床情報サイトでもASDでの高頻度を強調しています。
また、チックとの併存も注目され、常同運動症の約23%でチックが併存(6研究のレビュー)。ADHDや強迫症状の併存も一定割合でみられます。
5. なぜ起こるのか:神経生物学と遺伝研究のアップデート
基礎研究・画像研究は、皮質—線条体回路や抑制制御の偏り、GABA/グルタミン酸系の関与を示唆してきました。近年の遺伝学では、原発性の複雑性運動常同(pCMS)においてde novo の損傷性変異が有意に集積し、KDM5Bがハイ・コンフィデンスなリスク遺伝子として指摘されました。ASDやチック症との遺伝的オーバーラップも報告され、疾患横断的な神経発達的脆弱性の一端が見えつつあります(2023年)。
6. 生活への影響とリスク:自傷への備え
頭打ちつけ・眼突き・咬傷などの自傷は、皮膚損傷や視機能障害など重篤な転帰をもたらすことがあります。保護具(例:ヘルメット、手袋)や環境調整、作業療法の介入など安全第一の対策を優先しながら、行動の機能評価(何が引き金か)を並行して行うことが推奨されます。
7. 介入の実際:薬よりまず行動療法、そして環境づくり
7-1. 習慣逆転法(HRT)と在宅・親実施プログラム
HRT(Habit Reversal Training)は、気づきの訓練(Awareness Training)と競合反応訓練(Competing Response)を基本とする手続き。在宅で親が実施できるDVD/動画プログラムの臨床試験では、重症度尺度(SSS, SLAS)の有意な改善が確認され、電話支援付き在宅介入でも有効性が示されました(2016–2018)。
7-2. RIRDや強化スケジュールなどABA系の手続き
RIRD(応答遮断・リダイレクト)は、常同が始まった瞬間に別の適切な反応を促し、常同を中断→置き換える方法。ボーカル常同などで減少効果が複数研究で示されています。DRO(他行動強化)等の強化ベースの手続きも有効例が蓄積しています。個別化と一般化(他場面への波及)への配慮が成功の鍵です。
7-3. 学校・家庭での環境調整
- 予測可能なスケジュールと過剰刺激の調整
- 注意の切替えや代替行動の即時提示
- 記録(ABC記録)で引き金(Antecedent)→行動→結果を見える化し、機能に合った支援へつなぐ
- 自傷がある場合の安全対策(クッション材、保護具、配置換え)
7-4. 薬物療法の位置づけ
常同運動症そのものに確立した薬物療法はありません。ASDなど基礎疾患に伴う常同では薬物が検討されることもありますが、常同運動症単独に対する薬効を裏づける研究は限定的です。まずは行動療法と環境調整が推奨されます。
7-5. 身体活動(運動)介入のヒント
短時間の運動で一部の常同(例:手のフラッピング)が即時的に減ることが示された研究があります。常同のバイオメカニクスに合った運動を選ぶと効果的――という示唆もあり、休み時間の取り方や感覚運動のメニューを調整する際の参考になります。
8. 受診の目安と相談先
- 生活・学業・対人関係に障害が出ている/自傷がある
- ASD・ADHD・チックなどの併存が疑われる
- 行動が薬剤・てんかん・神経疾患等で説明できる可能性がある
→ 小児神経/児童精神・発達外来・作業療法へ。診断名は支援のための“言語化ツール”です。本人の困りごとを起点に、安全と生活の質を一歩ずつ整えることが大切です。
9. 最新トピックで変わる見立て:疾患横断の視点
- 診断分類:ICD-11でも神経発達症群に位置づけ、自傷の有無やチック・BFRB(体集中反復行動)の除外を明確化。臨床ではASD・チック・OCDとの「重なりと違い」を縦断的に評価することが求められます。
- 遺伝学の進展:KDM5Bなどの候補遺伝子が見えてきたことで、今後は発達期の回路形成に着目した介入(例:学習・感覚運動環境の最適化)の理論的裏づけが期待されます。
10. 今日から使えるミニ・チェックリスト
- 安全確保:自傷の有無、緊急時の連絡体制、必要な保護具
- ABC記録:いつ・どこで・何の後に増える?何を得る/避けるため?
- 環境調整:見通しの立つスケジュール、感覚刺激の調整、選択肢の提示
- HRTの導入:気づき→競合反応→称賛(家庭・学校で一貫して)
- ABA手続き:RIRDやDROなど、機能に合わせて個別化
- 専門職と連携:小児神経・児童精神・OT・学校と“同じ地図”で動く
まとめ
常同運動症は「ただのクセ」でも「すぐ薬で治すもの」でもありません。早期発達期に始まる反復運動が生活や安全に影響する時、診断名は支援の入り口になります。HRTやABA系の介入を中心に安全対策と環境最適化を進め、ASD・チック・OCDなど隣接領域の理解も合わせてアップデートしていきましょう。遺伝学や回路研究は、個に合った支援を設計するための手がかりを増やし続けています。
参考・出典(主要)
- DSM-5の整理:PsychDB「Stereotypic Movement Disorder」/日本語訳ガイドライン(学会)
- ICD-11 6A06 定義・除外基準:Find-A-Code(ICD-11 v2025-01)
- クリーブランド・クリニック(2025年レビュー、症状・治療方針・安全対策)
- 有病率・ASDとの関連:Frontiersレビュー(2017)、メタ解析(2020, 2023)
- 行動療法エビデンス:在宅親実施DVD試験(2016–2018)、RIRD/DROなどの研究レビュー
- 鑑別の要点・神経学的参照:MSDマニュアル(日本語)
- 遺伝学の最新:pCMSにおけるKDM5Bのリスク遺伝子報告(2023)
※本稿は医学的アドバイスではありません。自傷を含む症状や日常生活の妨げがある場合は、速やかに専門医・医療機関へご相談ください。