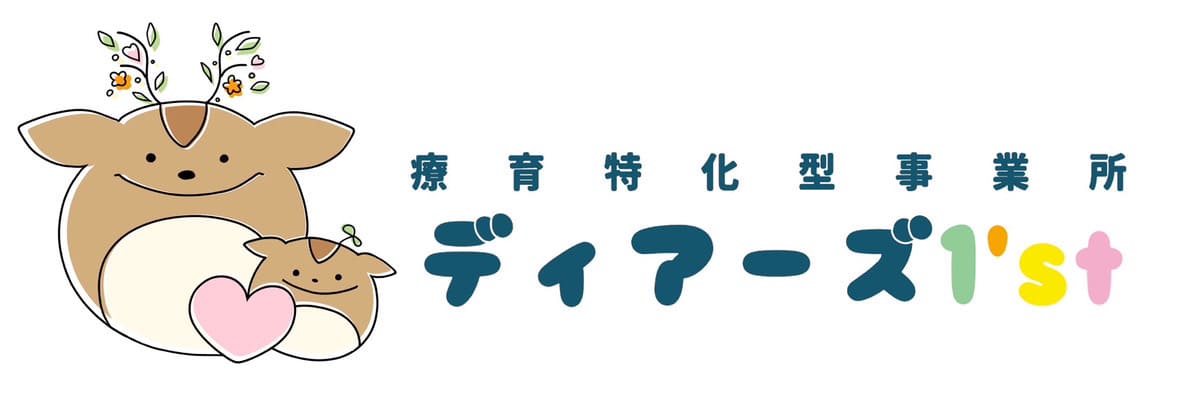目次
はじめに――「座っていられない」は努力不足ではない
まずは超シンプル解説:前庭覚と固有感覚って何?
あそび3選(家庭・園・学校でそのまま使える)
導入のコツ7か条(ここが勝敗を分ける!)
5分で作れる“座位ブースター・ミニルーティン
ケースのイメージ(家庭)
よくあるQ&A
禁忌・注意
観察チェックリスト(印刷して◎)
まとめ――“短く、気持ちよく、座る準備をする”
付録:必要なものミニリスト
ディアーズ1’st公式サイトへ
はじめに――「座っていられない」は努力不足ではない
「席に座ってもすぐ立ち歩いてしまう」「授業中や食事中に体がクネクネ動く」。こうした“座位の維持が難しい”様子は、意志や礼儀の問題として片づけられがちですが、多くの子どもでは感覚処理(センサリープロセシング)の特性が背景にあります。
なかでも鍵になるのが前庭覚と固有感覚。これらを満たす適切な“あそび”を日常に少し仕込むだけで、座位や集中のしやすさが目に見えて変わります。本記事では、家庭・園・学校で取り入れやすい前庭・固有感覚あそび3選と、導入のコツを具体的に解説します。
まずは超シンプル解説:前庭覚と固有感覚って何?
- 前庭覚(ぜんていかく):耳の奥(内耳)にある前庭器官が受け取る、回転・傾き・加速度の情報。体の向きや動きを把握し、姿勢や目の動きを安定させます。
- 固有感覚(こゆうかんかく):筋肉や関節にあるセンサーが受け取る、力加減や体の位置の情報。体をどのくらい力強く・どの位置で保つかを脳に知らせ、姿勢保持に直結します。
座位が続かない子は、多くの場合「体の位置や力加減の“地図”がぼやけやすい」「動きの刺激をもっと欲している/逆に刺激に敏感で落ち着きにくい」などの状態にあります。
そこで、短時間で安全に“ちょうどよい刺激”を入れることがポイントになります。
あそび3選(家庭・園・学校でそのまま使える)
1. ブランコ&ハンモック“ゆらゆら”セット(前庭覚メイン+固有感覚サブ)
ねらい:ゆっくりした前後・左右の揺れで前庭を整え、姿勢と眼球運動の安定を促す。ハンモックの“包まれ感”で安心もプラス。
やり方
- 速度は“ゆっくり・規則的”が基本。 10〜30秒同方向→一時停止→逆方向、と予測可能なリズムで。
- 数を数える・歌うなどリズム付けをして、終わりを予告(例:「10回こいだらおしまい」)。
- ハンモックは体を包み込む姿勢(膝を軽く曲げる)で1〜3分。“ぎゅっ”と布に押される軽い圧(固有感覚)が落ち着きを助けます。
安全のコツ
- 目が回りやすい子は回転(グルグル)を避け、前後・左右の直線揺れから。
- 顔色・表情・呼吸を観察し、過刺激サイン(青白い・眉間にしわ・無言になる)が出たら即休憩。
座位へのつなげ方(リレー)
- 揺れ→深呼吸3回→席に戻り“10分タイマー”で学習へ。
- 「揺れは“準備運動”、席で“本番”」と言葉でルール化。
2. ミニトランポリン/バランスボード“3分サーキット”(前庭+固有感覚の同時刺激)
ねらい:上下動や微調整で前庭を活性化しつつ、足関節・体幹の固有感覚を入れて姿勢制御の精度を上げる。
用意:ミニトランポリン(または踏み台)、バランスボード(なければ厚めクッションでも可)、床に貼るテープ(ライン)。
1セット(約3分)
- ラインジャンプ:テープをまたいで前後に10回、左右に10回(足はそろえ、小さく静かに)。
- ミニトランポリン:やさしい弾み20回。目線は前、腕は軽く振る。
- バランスボード:10〜20秒×2回静止。できれば目を“点”に固定(視線安定)。
ポイント
- 音や掛け声で一定のリズムを作る。メトロノームアプリや好きな曲のカウント8×2など。
- 元気が有り余る子は2セット、敏感な子は各メニュー半分から。
座位へのつなげ方
- 最後に“握る・押す”の深圧(後述のセラバンド握りなど)→水分ひと口→席へ。
- サーキット後の最初の課題は成功しやすいもの(計算プリントの1段目だけ等)。
3. “重いもの運び”&“抵抗運動”(固有感覚どっさり)
ねらい:関節にじっくり圧が入る仕事をすることで、体の地図を“くっきり”に。落ち着き・持久座位に直結。
例
- お手伝い運搬:水入りペットボトルを袋に入れて部屋から部屋へ、本の束を本棚へ。
- イス押しレース:空のイスを静かにゆっくり10メートル押す(床に傷がつかない環境で)。
- タオル綱引き:保護者や先生と座位でタオル引き(3回勝負)。
- 壁押し:両手を壁に当て、5秒押す→5秒休む×5セット。
- セラバンド/タイヤチューブでの握る・引く(机の脚に結び、両手で10回)。
安全のコツ
- “重さ”は本人が笑顔で話せる程度。息が止まる・眉をしかめるなら軽く。
- 関節に痛みがある日は中止。
座位へのつなげ方
- 終わりに手指の深圧(指を一本ずつ“にぎにぎ”5秒)→鉛筆を持つ→課題開始。
- 課題中も机下に足用セラバンドを張り、ふくらはぎで軽く押すことで固有感覚を補給。
導入のコツ7か条(ここが勝敗を分ける!)
- 観察から始める:どの刺激で表情が和らぐか/集中が伸びるかをメモ。合わない刺激は“やらない勇気”。
- ルーティン化:開始合図→メニュー→終了合図→座位、を同じ順番・同じ言葉で。
- 短く・頻回に:1回3分以内を1〜3時間おき。長すぎると疲れて逆効果。
- 予告と選択肢:終わりを可視化(タイマー・砂時計)、メニューはA/Bの二択で本人の主体性を確保。
- 成功の即フィードバック:「いま背中がまっすぐ!」など具体的に称賛。脳が“これが正解”と学習。
- 環境も整える:足台、机下セラバンド、お尻の浅掛け→深掛け指示、鉛筆の太軸など。
- 過刺激のブレーキ:顔色悪化、黙り込む、あくび連発は“やり過ぎサイン”。60〜90秒の休憩+水分でリセット。
5分で作れる“座位ブースター・ミニルーティン”
- ①前庭ウォームアップ(30〜60秒):ブランコゆっくり10回 or ラインジャンプ前後10回
- ②固有ドリル(60〜90秒):壁押し5秒×5 + セラバンド引き10回
- ③クールダウン(30秒):深呼吸3回 + 手指にぎにぎ
- ④座位へ(10〜15分):タイマーを可視化し、終わったらシール1枚
ケースのイメージ(家庭)
- 小1・Aくん:食事で3分ほどで離席。
- 介入:食前にタオル綱引き3回→ハンモック1分→深呼吸。机下に足バンド。
- 結果イメージ:初週で着席7〜10分に。2週目は話しかけなければ最後まで座れる日も。
※実際の変化は個人差あり。無理に引き延ばすより“気持ちよく座れる時間”を積むことが大切。
よくあるQ&A
Q1:毎日やらないと効果が出ませんか?
A:短時間×高頻度が合言葉。毎日1回長くより、1日2〜3回の小分けが◎。
Q2:回転が大好きで、グルグル止まりません。
A:回転は刺激が強く、余韻が残りやすいため、座位前は控えめに。直線揺れや上下の小さな弾みへ誘導を。
Q3:やっても逆に落ち着かないことがある。
A:刺激量が多い/リズムが不規則/終わりが見えないのどれかが原因になりがち。
タイマーで終わりを固定し、回数・秒数を下げる、最後に深呼吸→水分を入れて調整。
Q4:学校で目立たずにできる方法は?
A:机下セラバンド押し、握力ボール、足台、プリント配布の“お仕事”運搬など“静かな固有感覚”を。
禁忌・注意
- めまい・乗り物酔いが強い、てんかん既往、頚部の整形外科的問題がある場合は、前庭刺激は慎重に。医療者と相談を。
- 痛みを伴う動きは中止。
- 幼児・低学年は必ず大人が見守り、環境の安全を確保(床の滑り止め、周囲のスペース確保)。
観察チェックリスト(印刷して◎)
- 刺激前後で姿勢(背中・首)がどう変わる?
- 視線は安定する?目がキョロキョロ減る?
- 手先の力加減(鉛筆が強すぎ/弱すぎ)が整う?
- 表情・呼吸は楽そう?
- 座位時間は何分→何分に?(日付とともに記録)
まとめ――“短く、気持ちよく、座る準備をする”
座位が続かない背景には、前庭覚と固有感覚の“燃料不足”が潜んでいることが少なくありません。
本記事の3つのあそび(ゆらゆらセット/3分サーキット/重いもの&抵抗運動)を、短時間×規則的リズム×可視化のコツで回すことで、姿勢と集中の土台が整っていきます。
まずは1日2回・各3分から。子どもが“気持ちいい”と感じる線を一緒に探り、座る前の準備習慣に育てていきましょう。
付録:必要なものミニリスト
- ブランコ/ハンモック(家庭なら布製ハンモック、学校は屋内ボードブランコも)
- ミニトランポリン or 厚めクッション、テープ(ライン用)
- セラバンド or タイヤチューブ、握力ボール、足台
- タイマー(砂時計・キッチンタイマー・アプリ)
今日の一歩が、明日の“座れるじぶん”をつくります。
ディアーズ1’st公式サイトへ
「評価して、支援して、振り返る」——この基本を丁寧に。ディアーズ1’stは、学校・家庭・関係機関との連携まで見据えた療育を提供します。対象エリア:横浜市(鶴見区・神奈川区)、川崎市(川崎区・幸区)ほか近隣。
👉 ディアーズ1’st公式サイトへ/通所可否・見学の流れ・費用などは相談フォームでご質問ください。