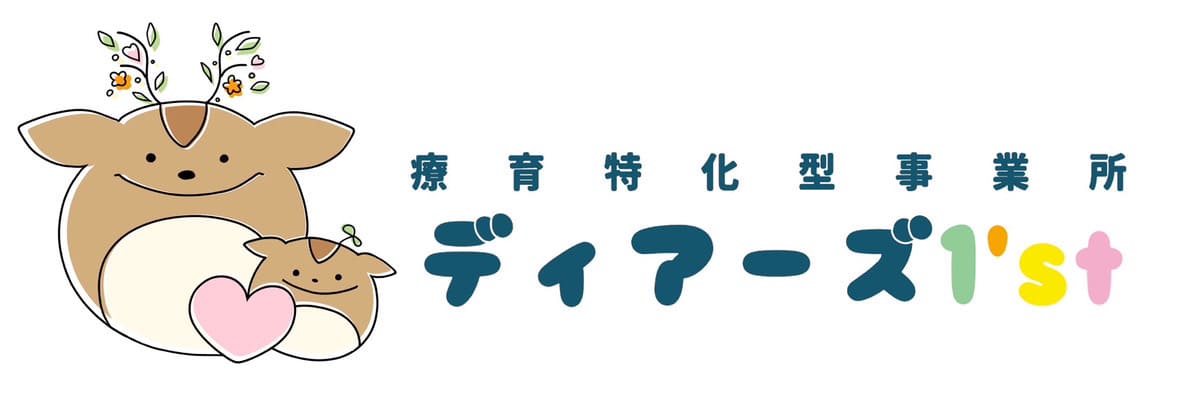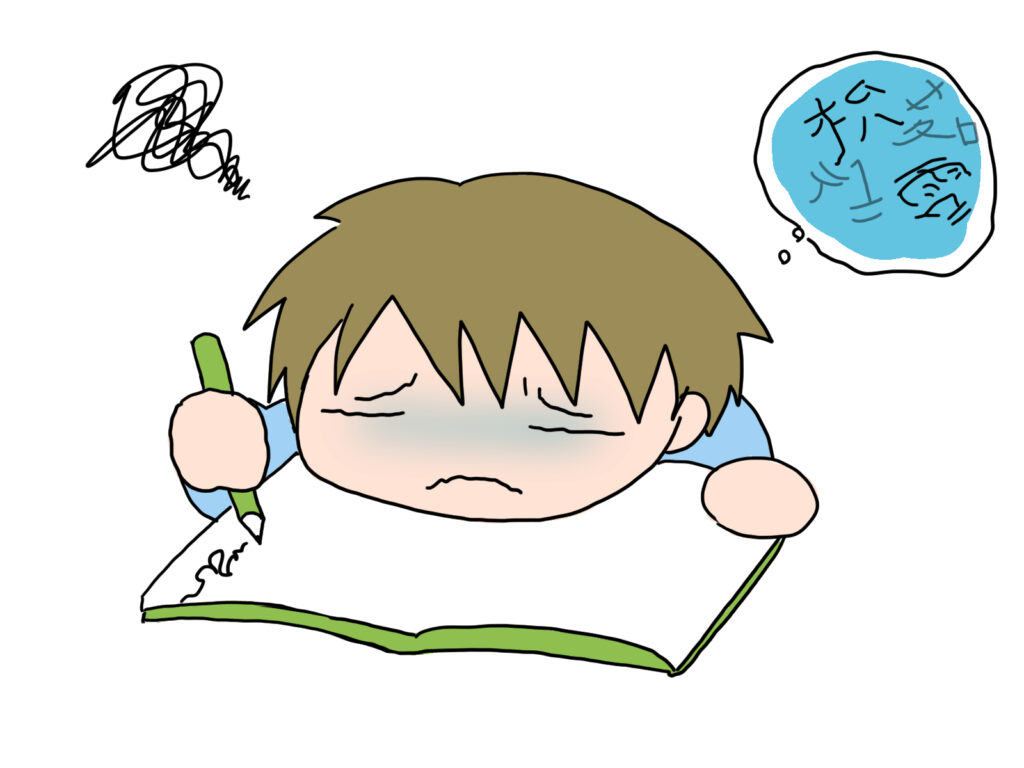
目次
はじめに:いま必要な「正しい理解」
LDの定義と分類:日本の定義×国際基準を押さえる
どんな特徴が見られるか:領域別の具体像
早期発見のタイミングとサイン
どう評価を受けるか:学校・医療・地域での導線
学びを支える実践:授業づくり・家庭・ICT
法制度と社会の最新動向:学校から社会へ
まず何をすればいい?ミニ・アクションリスト
まとめ:学びを「その人らしさ」に合わせる
参考・信頼できる情報源
お困りのときは専門家へご相談を──療育特化型事業所「ディアーズ1'st」のご案内
はじめに:いま必要な「正しい理解」
学習障害(LD)は、知的発達に大きな遅れがないにもかかわらず、読み・書き・計算など特定の学習技能に著しい困難が続く神経発達症の一つです。日本の学校現場では、学習面や行動面で顕著な困難をもつ児童生徒が小中で約8.8%との調査もあり、どのクラスにも支援が必要な子がいる現実があります。早期に気づき、適切な支援につなげることが、その後の学び・自己肯定感・進学就労の土台を大きく変えます。(厚生労働省)
LDの定義と分類:日本の定義×国際基準を押さえる
日本(文部科学省)の定義
全般的な知的発達に遅れはないが、「聞く・話す・読む・書く・計算・推論」といった基礎能力の一部に習得や発揮の困難があり、学習上さまざまな困難に直面している状態を指します。(文部科学省)
国際的な医学的分類
・DSM-5-TRではSpecific Learning Disorder(SLD)として、読み・書字表出・数学のいずれか(または複数)の領域で、十分な指導にもかかわらず6か月以上困難が持続することなどが診断要件です。推定有病率は学齢児の約5~15%。(psychiatry.org)
・ICD-11ではDevelopmental Learning Disorder(発達性学習障害)として、読み(ディスレクシア)/書字表出(ディスグラフィア)/数学(ディスカリキュリア)の下位分類が整理されています。(iris.who.int)
用語メモ
・ディスレクシア:読みの正確さ/流暢さ/理解に持続的な困難。
・ディスグラフィア:綴り、文法・句読点、文章構成など書字表出の困難。
・ディスカリキュリア:数概念、計算、算数推論の困難。(psychiatry.org)
“障害(disorder)”と“ディスアビリティ(disability)”の違い
医学的な障害(disorder)は個人の認知神経特性に由来する状態、ディスアビリティは環境要求とのミスマッチで生じる不利を指します。環境調整で学びや参加の障壁は減らせます。(uwo.ca)
どんな特徴が見られるか:領域別の具体像
・読み(ディスレクシア):語の正確さ・流暢さが伸びにくい/音韻操作(音の分解・合成)が苦手/読むのに過大な努力が必要で内容理解が追いつかない。
・書字表出:綴りの誤りが慢性的に続く/文法・句読点・構成に難しさ/書く速さが極端に遅い。
・数学:数概念の形成が遅い/暗算・筆算が極端に難しい/文章題で式を立てにくい。
・共通して:処理速度やワーキングメモリの弱さ、ADHDや不安症との併存も少なくありません。(psychiatry.org)
早期発見のタイミングとサイン
幼児期(就学前)
日本では1歳6か月・3歳児健診が全自治体で実施され、発達の気がかりを拾い上げる仕組みがあります。就学前では言語発達・音への気づき(韻・音節)・命名スピード(RAN)などが後の読み書きに関わります。(中央淡水魚研究所)
気づきの例
・ことば遊び(しりとり・韻探し)が極端に苦手/文字と音の対応がなかなか結びつかない
・図形・数の概念化に強い抵抗がある(数を量として捉えにくい)(J-STAGE)
小学校低学年
・ひらがな・カタカナの音読の正確さ・速さが学年平均から大きく遅れる
・仮名→音の変換や漢字の音読・書き取りの習得に著しい困難
・数の大小比較・繰り上がり繰り下がり・文章題の式立てで著しい苦手さが持続
日本語では、ひらがな音読やSTRAW-R(標準読み書きスクリーニング検査)などの検査がスクリーニングやアセスメントに用いられます。(サクセス・ベル)
中学以降・成人
・学習量増加で処理速度の遅さが目立つ/長文読解やレポート作成で疲弊
・数学は基礎計算よりも数学的推論の持続的困難が目立つことも。(findacode.com)
どう評価を受けるか:学校・医療・地域での導線
1. 学校での相談:担任・特別支援教育コーディネーターに学習の躓きを共有。学校内での観察・経過整理、必要に応じて通級による指導につなげます。(文部科学省)
2. 専門アセスメント:心理検査(知能・注意・記憶など)と読み書きの標準化検査(例:STRAW-R)を組み合わせ、プロフィールを可視化します。(世田谷区桜新町の小児科 さくらキッズくりにっく)
3. 地域の相談窓口:各都道府県の発達障害者支援センターは、診断の有無に関係なく無料で相談可能。必要に応じて医療・教育・福祉と連携します。(リハビリテーション情報提供サイト)
学びを支える実践:授業づくり・家庭・ICT
授業内の「ユニバーサル」から始める
・学習のユニバーサルデザイン(UDL)と三層モデル(全員向け→小集団→個別)で、できる環境を前提化。課題の提示方法、視覚化、選べる提出手段などを整えます。(nits.go.jp)
個に応じた学習方法(指導×補償)
・読み:音韻意識・文字音対応・語彙・読解を系統的・反復的に教える(構造化リテラシー)。音読は「短く頻回」に。
・書字表出:作文の骨組みテンプレート、語の下書き→推敲の段階化、予測変換・スペルチェックの活用。
・数学:数概念は「具体物→図→記号」の段階で、多感覚に定着。問題文は語彙を整理し、視覚的に構造化。
・ICT・合理的配慮(例):タブレット使用、音声読み上げ・読み上げソフト、テキストデータ配布、試験時間延長、口頭試問等。日本の指針でも配慮例として示されています。(文部科学省)
専門用語メモ
・合理的配慮:学ぶ権利を保障するために、過重な負担にならない範囲で環境や方法を調整すること(例:時間延長、別室受験、ICT利用など)。(文部科学省)
家庭でできる支援
・宿題は時間と量を調整し、短いセッションで成功体験を積み重ねる
・読書は音声併用(オーディオブック+紙/電子)で理解優先
・書く課題はキーボード入力・音声入力も選択肢に
・得意領域(図工・スポーツ・プログラミング等)を日常的に可視化して自己効力感を育てる
法制度と社会の最新動向:学校から社会へ
2024年4月からは、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化され、学校を出た後の高等教育・就労でも環境調整が前提になりつつあります。読み書き・計算の困難は試験方式の柔軟化や業務支援ツールで十分に補える時代です。(政府オンライン)
まず何をすればいい?ミニ・アクションリスト
・気づきの記録:いつ・どの課題で・どの程度困るかをメモ(テストやノートのコピーも保管)
・学校に相談:担任・コーディネーターへ共有。合理的配慮の試行をお願いする
・専門評価:必要に応じて医療機関/心理職による検査+読み書き検査(STRAW-R等)
・地域につながる:最寄りの発達障害者支援センターに連絡し、学齢期~進学・就労までの見通しを一緒に描く (サクセス・ベル)
まとめ:学びを「その人らしさ」に合わせる
LDは「できない子の問題」ではなく、認知特性と学びの設計の相性の問題です。国際基準(DSM-5-TR/ICD-11)と日本の定義を踏まえ、早期の気づき→適切な評価→指導と合理的配慮→学びの継続を回すことが何よりの支援です。学ぶ方法を変えれば、学ぶ権利は必ず守れます。(psychiatry.org)
参考・信頼できる情報源
・文部科学省「学習障害(LD)」解説ページ/配慮例、ICT活用ハンドブック (文部科学省)
・APA(米国精神医学会)SLD解説(診断・有病率・支援) (psychiatry.org)
・WHO『ICD-11 精神・行動・神経発達症の臨床記述と診断要件(2024)』 (iris.who.int)
・学校の読み書き支援体制と合理的配慮の実例(講演資料) (文部科学省)
・UDLと三層モデル(研修資料) (nits.go.jp)
・発達障害者支援センター一覧(全国) (リハビリテーション情報提供サイト)
本稿は2025年9月時点の公開情報に基づき作成しています。制度や手引きは自治体・学校で運用が異なることがあるため、最新情報は各機関の窓口でご確認ください。
お困りのときは専門家へご相談を──療育特化型事業所「ディアーズ1'st」のご案内
学びのつまずきに早く気づき、具体的な支援計画(アセスメント→支援→振り返り)へとつなげることが、子どもの自己肯定感と将来の選択肢を広げます。療育特化型事業所「ディアーズ1'st」では、日々の困りごとの整理や、学校・家庭・関係機関との連携の進め方についての相談先として活用できます。横浜市(鶴見区・神奈川区)や川崎市(川崎区)をはじめ、近隣エリアで児童発達支援や放課後等デイサービス(児発・放デイ)の利用を検討されているご家庭は、まずは下記より情報をご確認ください。ニーズや発達特性、通所の可否、見学や相談の流れなど、療育に関する初歩的な質問からでも大丈夫です。
👉 詳しくは 療育特化型事業所ディアーズ1'st 公式サイト へ。
「わが家のケースでは何から始めればいい?」という段階でも、相談フォームからお気軽にお問い合わせください。